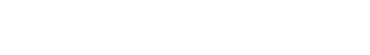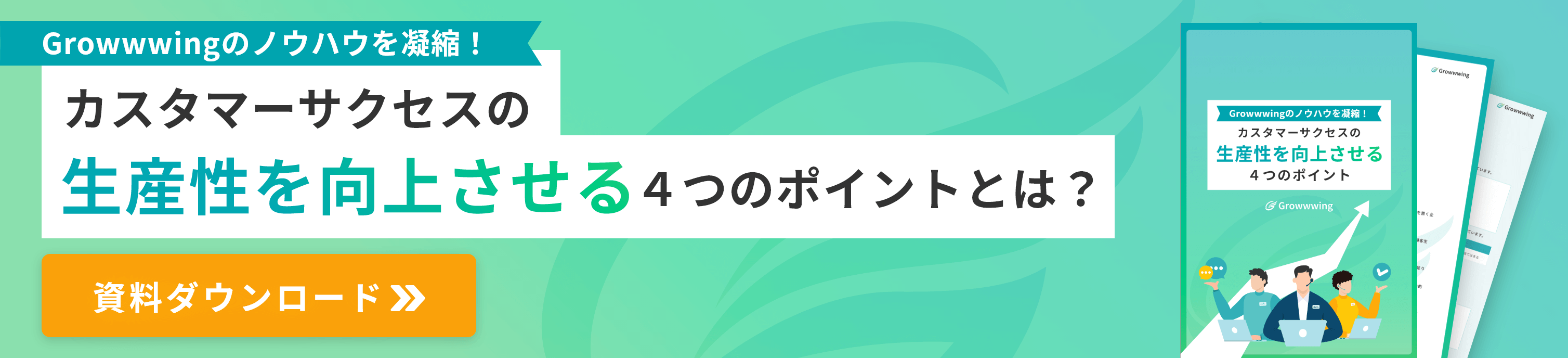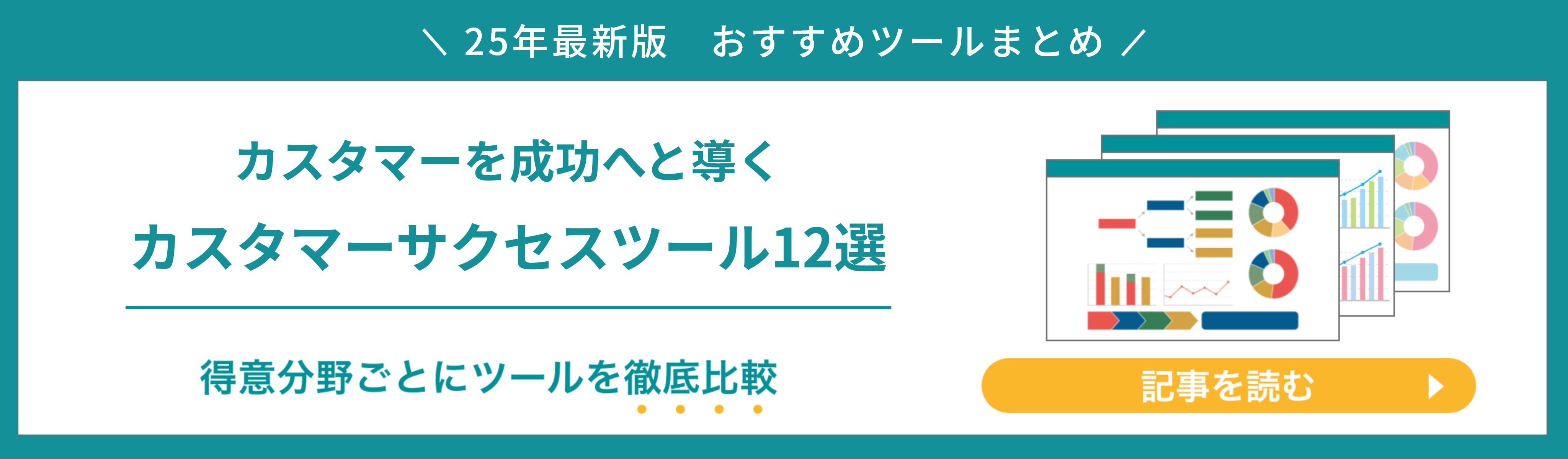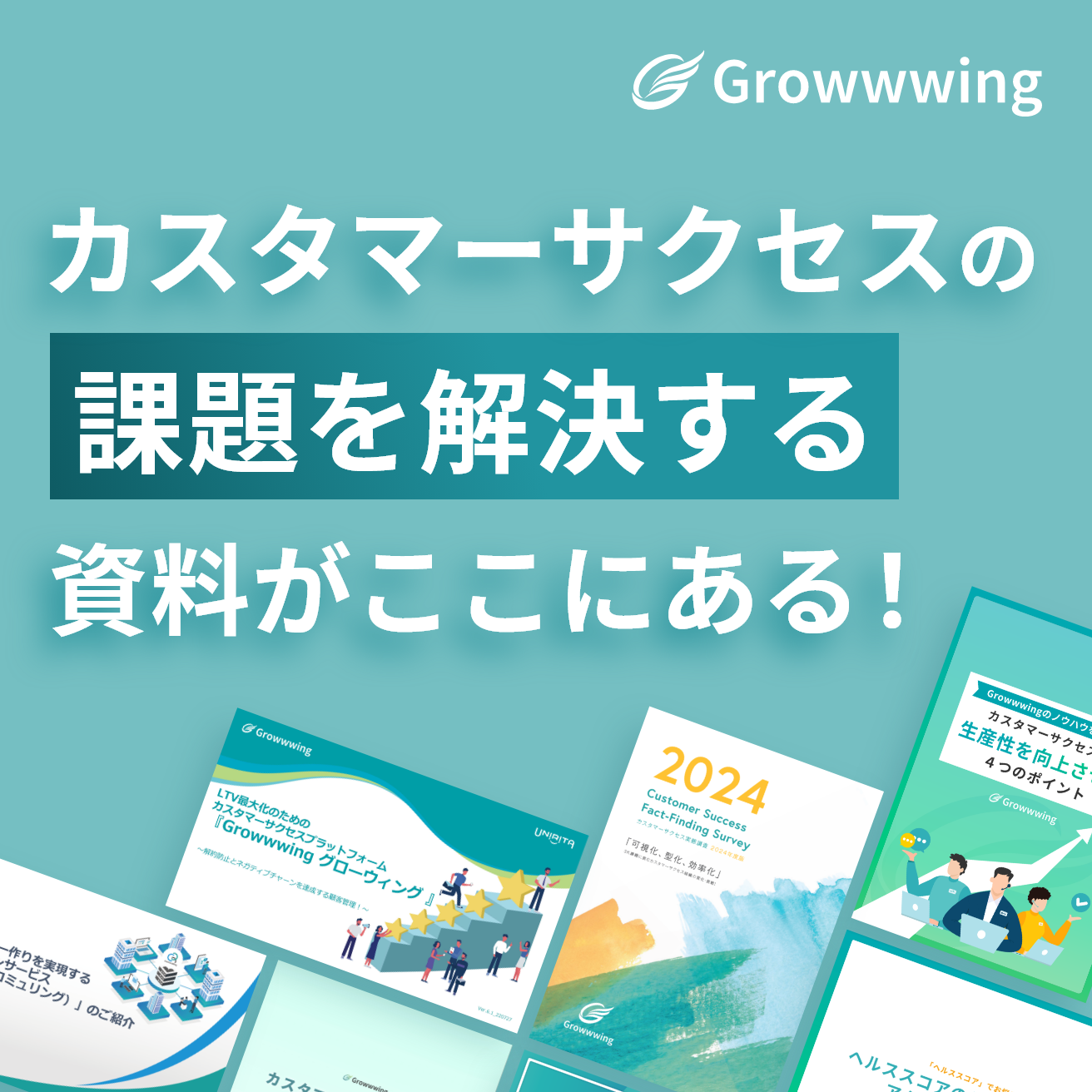【応用編】ヘルススコア設計後の改善アクションの重要性

ヘルススコア(health score)は、SaaS/サブスクリプションのカスタマーサクセスにおいて、顧客の健康状態を可視化するための指標です。
ヘルススコアの設計が適切かつ結果が良好な場合、顧客がプロダクトやサービスに価値を感じており、継続的に利用する可能性が高いと判断できます。
ヘルススコアの役割は、顧客の健康状態を「可視化」するものですが、目的はその先にあります。
ヘルススコアを設計/可視化した後は、ヘルススコアに基づいたカスタマーサクセス施策を立案・実践し、そこから得られた気付きをヘルススコアの設計にフィードバックし、次のカスタマーサクセス施策立案・実践に繋げていく。このPDCAサイクルを回すことで、より顧客の実状に即したヘルススコアに近づくことができます。
本記事では、ヘルススコア設計後の継続的改善の重要性をわかりやすく解説します。
PDCAサイクルの重要性

基礎編と実践編では、SaaS/サブスクリプションにおけるヘルススコアの役割やメリット、設計方法を簡単に解説しました。
今回の応用編では、ヘルススコア設計後の活動や改善に着目し、PDCAサイクルの重要性を説明していきます。
SaaS/サブスクリプションのカスタマーサクセス活動では、主に顧客がプロダクトやサービスを継続的に利用するかどうかを計測するためにヘルススコアを設計します。
ヘルススコアが良好な顧客にはアップセルやクロスセルの提案、ヘルススコアが低い顧客には解約を防ぐためのフォローなど、ネガティブをポジティブに変えるためのアクションを実施します。
ヘルススコアの設計を初めてした場合は、その精度に疑問を持たれるかと思います。実際に、初めて設計したヘルススコアで顧客の健康状態を完璧に把握できている企業は非常に少ないと思われます。
ヘルススコアの精度を高めていくには、設計後にPDCAサイクルを回し、結果をしっかりと設計と運用にフィードバック・改善していく必要があります。
ヘルススコアを用いてカスタマーサクセス活動を成功させるには、設計して終わりにせず、継続的に改善するためのPDCAサイクルが重要だということです。
| ステップ | 施策例 |
|---|---|
| Plan(計画) | ◆自社の製品やサービスに合った、ヘルススコアの要件や算出ロジックとアクションプランを設計する(初回のみ) ◆(Actionを受けて)ヘルススコアの算出ロジックとアクションプランを再設計する(2回目以降) |
| Do(実行) | ◆顧客ごとのヘルススコアを計測する ◆ヘルススコアに応じたカスタマーサクセス施策を実行し、プロアクティブな提案によって、顧客の不安や不満を未然に解消する。また、ヘルススコアが健全な顧客にはアップセル/クロスセルを提案し、顧客単価を向上させる。 |
| Check(評価) | ◆ヘルススコアの値が実際にアプローチした顧客の実状と整合性がとれていたかを評価する ◆問題・課題を顧客が感じていた場合、提案内容は正しかったかを評価する ◆解約が発生した場合、その原因調査と、未然に防げたはずの解約・解約防止計画の言語化 |
| Action(改善) | ◆Check(評価)で洗い出したフィードバックに優先度をつけ、ヘルススコアの改善をおこなう。 ※ヘルススコアだけでなく、カスタマージャーニーマップやコンテンツ、トークスクリプト等も改善をおこなっていく |
たとえば、解約率(チャーンレート)の低下を最重要課題とみる場合は、解約につながる兆候が表れやすいロジックを組み、ヘルススコアの設計を見直します。
PDCAサイクルを回し、カスタマーサクセス活動の実践評価から、改善要望や追加の検討事項をフィードバックすることで、より顧客の実状を表現するヘルススコアの設計が可能になります。
このようにヘルススコアを用いたカスタマーサクセス施策の計画、実践、評価、改善のフィードバックループをおこなうのが、ヘルススコアのPDCAサイクルです。
カスタマーサクセスツールを導入する場合は、ヘルススコアの要件やロジックを柔軟に修正できる製品を選びましょう。
ヘルススコアは定期的に更新したものを計測
ヘルススコアは、ダッシュボード等のいつでも見える場所に可視化しましょう。ただし、リアルタイムで更新する必要はありません。プロダクトやサービスの特性、カスタマーサクセスメンバーのアクションタイミングを考慮し、日次や月次等で定期的に更新しましょう。
リアルタイムで計測できるのがベストではありますが、複数のデータを掛け合わせて実装することが多いヘルススコア計算をリアルタイムに計測できる仕組みはほとんどありません。また、ヘルススコアがリアルタイムでも実践する人は当日の計画タスクが決まっていることがほとんどですから日次更新であってもあまり影響はありません。さらに、ヘルススコアは定期的に改善が行われることから、リアルタイム性よりもメンテナンス性やロジック変更への柔軟性・簡易性に重きをおいてツールや仕組みを検討しましょう。
メンテナンス性やロジック変更への柔軟性・簡易性に重きをおいてヘルススコアを計測することによる、メリットは4つあります。
◆エンジニアのようなスキルセットがなくても現場で、改善後のロジックを実装できる
◆施策の実行結果から、ヘルススコア設計に大幅な見直しが発生しても対応ができる。
◆リアルタイムではないので、改修したヘルススコアを公開するタイミングを調整しやすい。
もっとも大きなメリットは、ヘルススコアを柔軟かつ早期に改善し、すばやく改善後のアクションを起こせる点です。
カスタマーサクセス活動では、ちょっとした状況判断の遅れが原因となり、客離れやサービス解約につながる可能性やアップセル/クロスセルの機会を逸してしまう可能性がありますので、期や年度が終わらないとヘルススコアの改修ができない、エンジニアのリソースが確保できないと改善ができないといった状況は致命的になります。
ヘルススコアの変化と、達成したい指標が連動しているか確認
ヘルススコアを運用することで改善されることが期待できる指標は数多くありますが、なかでも効果があらわれやすいのが、チャーンレート(解約率)と顧客単価(MRR/ARR)の2点です。
着目点1. チャーンレート
チャーンレート(解約率)は、SaaS/サブスクリプションのカスタマーサクセス活動でもっとも重要な指標のひとつです。
チャーンレートが高い場合、製品やサービスを解約する顧客が多いということであり、LTVの減少に直結します。
ヘルススコアを計測することで、チャーンの可能性が高い顧客を洗い出し、未然にアクションを起こすことができます。
たとえば、チャーンレートにつながりやすい要素として、ログイン率の低下が挙げられます。
ログイン率が以前より低くなっている顧客は、サービスを利用する機会が少なくなっており、解約の可能性が高いと判断できるためです。
自社のプロダクトやサービス特性に応じて、解約の原因になりやすい要素をヘルススコアの指標に組み込めば、解約の兆候が表れた顧客を発見しやすくなります。
着目点2. 顧客単価(MRR/ARR)
顧客単価(MRR/ARR)は、現在利用しているサービスのアップグレードやオプション購入といったアップセル、現状提供しているサービスとは別の課題解決をおこなうサービスを追加契約いただくクロスセルによって向上します。
アップセル・クロスセルが成功しやすい顧客の利用状態を定義し、ヘルススコアを設計することで、提案すべき顧客を効率的かつ効果的に洗い出せます。
たとえば、一定期間中のサービス利用回数や、利用している機能、参加したイベントのアンケートやHPの閲覧状況などが挙げられます。
達成したい指標と連動する形でヘルススコアを設計し、見える化することで、さまざまな角度からアプローチする価値の高い顧客を発見できます。
ヘルススコアに応じてアクションを
ヘルススコアは設計して終わりにせず、より実状に即したヘルススコア設計を探りながら、PDCAサイクルを回していくことが大切です。
チャーンレートの低下や、顧客単価(MRR/ARR)の向上など、達成したい指標に連動する形でヘルススコアを設計し、効率的かつ効果的にアクションを起こす仕組みが必要になります。
計測後のアクションは定型化しておく
カスタマーサクセス活動において、ヘルススコアを計測し、PDCAサイクルを回す重要性を説明しました。
PDCAサイクルを高速で回し、すばやくアクションを起こすためには、あらかじめヘルススコア計測後のアクションを定型化しておく必要があります。
そこで役に立つのが「CTA(Call to Action)」と「プレイブック」です。
CTA(Call to Action)は「行動喚起」のことで、ヘルススコアや利用状況が特定の結果になった際に、何かしらのアクションを促すことをさします。
一方、プレイブックは、アクションの型を事前に定義する概念になります。「どのようなデータが発生したら、顧客にどのようなアクションをおこなうか」といった行動リストやルールを事前に定型化する、という考え方になります。
誰が・なぜ・いつ・どこで・なにを・どのようにするのか(5W1H)をプレイブックとして「型化」しておくことで、CS組織の経験が少ない社員でもヘルススコアの変化に応じて適切にアクションできます。
ヘルススコア設計後のDo(実行)による変化を計測
ヘルススコア設計後のDo(実行)により、顧客のヘルススコアにどのような影響が出たかも忘れずに計測しましょう。
カスタマーサクセス活動は、ヘルススコアの設計、実行、評価、改善のPDCAサイクルの繰り返しであり、終わることのないものだということを再認識しましょう。
ヘルススコアは自社組織の管理につながる
 ヘルススコアは、顧客の「健康状態」を測るためだけのツールではありません。
ヘルススコアは、顧客の「健康状態」を測るためだけのツールではありません。
ヘルススコアを活かしたCS組織の管理方法を解説します。
顧客管理状況は自社の状態も反映する
ヘルススコアの数値(顧客の管理状況)は、自社のCS組織の状態を反映しています。
たとえば、ヘルススコアが高い状態が続いている場合、自社のCS組織が十分な成果を上げており、パフォーマンスが高いことがわかります。
ヘルススコアを追跡することにより、自社のCS組織の業務品質や目標達成度を評価することも可能です。
このようにヘルススコアは、顧客の健康状態を測る以外にも、さまざまな活用方法があります。
まとめ
ヘルススコアはカスタマーサクセスの実現に欠かせない指標のひとつです。
ヘルススコアの設計後、顧客の健康状態に応じたアクションをとることで、LTVを最大化したり、チャーンレートの上昇を防いだりすることができます。
しかし、ヘルススコアは設計したら終わりではありません。
むしろ、ヘルススコアを設計した後の改善アクションこそが大切です。
ヘルススコアの計測によってカスタマーサクセス活動の改善点が判明した場合、さらに深掘りしたい点や可視化したい点をヘルススコアの設計にフィードバックし、要件やロジックを見直しましょう。
ヘルススコアの設計、実行、評価、改善のPDCAサイクルを繰り返すことで、より実状に即したヘルススコア分析に近づきます。
ヘルススコアのPDCAサイクルを回すため、リアルタイム性よりもメンテナンス性やロジック変更への柔軟性・簡易性に重きをおいてツールを選びましょう。
執筆者情報:
渡邉 剛(わたなべ ごう)
ユニリタ自社開発のETLツール「Waha! Transformer」の導入教育/サポート、データ活用システム(ETL/DWH/BI)構築のプロジェクトマネージャーを歴任し、2018年にカスタマーサクセスチームの立上げ責任者を担当。
その経験からカスタマーサクセス専用ツールの必要性を実感し「Growwwing」の事業立上げをおこなう。
2020年7月の事業化からプロダクトマーケティングとカスタマーサクセスの責任者を担当。
カスタマーサクセスコミュニティ「CS KOMMONS」においてハイタッチ部 副部長も歴任。
『Growwwing 』サービス資料を無料でダウンロード
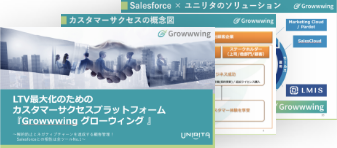
LTV最大化のためのカスタマーサクセスプラットフォーム『Growwwing グローウィング』のサービス資料を無料でダウンロードいただけます。
『Growwwing グローウィング 』は、解約防止とネガティブチャーンを達成する顧客管理が実現。Salesforceとの相性は全ツールNo.1です。