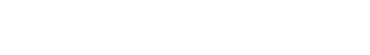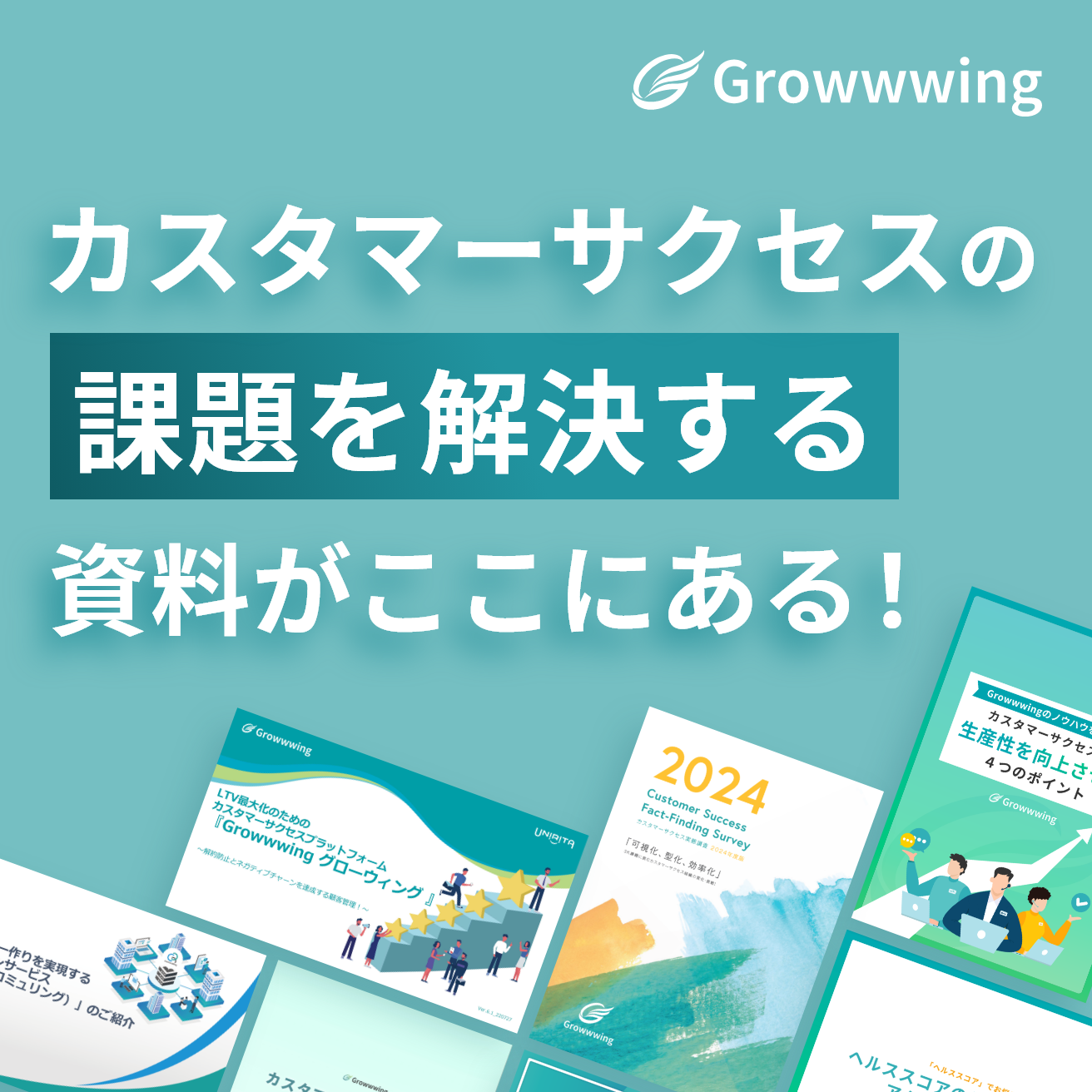【基礎編】そのスコア、本当に使えていますか?ヘルススコアの基本と活用法

解約率の低減やアップセルの機会創出に向け、顧客の状態を可視化する「ヘルススコア」の重要性が高まっています。カスタマーサクセスにおいて、ヘルススコアは単なる数値ではなく、顧客の“今”を捉え、次のアクションを導くための指標です。本記事では、ヘルススコアとは何かという基本から、その設計方法や組み込むべき指標、営業・CS・プロダクト各部門での活用例までを、丁寧に解説します。また、導入時の注意点や失敗しがちな落とし穴、スコアの見方・活かし方についても実践的な視点で触れています。SaaS企業やサブスクリプションモデルに取り組む方、カスタマーサクセスにこれから携わる方に向けた、ヘルススコアの基礎理解に最適な内容です。
カスタマーサクセスにおけるヘルススコアの位置づけ

ヘルススコアという言葉はカスタマーサクセスの現場で用いられることが多く、単なる数値の羅列ではなく、顧客との関係性をマネジメントするための“共通言語”といえる存在です。
カスタマーサクセスは、単に「顧客対応のよしあし」で語れる活動ではありません。製品の利用状況、契約継続の意思、担当者の満足度、サポート履歴、将来的なアップセル・クロスセルの可能性など、あらゆる要素が複雑に絡み合います。これらをチームや部署を越えて同じ視点で把握するためには、客観的かつ定量的な指標が不可欠です。その役割を果たすのがヘルススコアです。営業・カスタマーサクセス・マーケティング・プロダクト開発などの複数部門が、顧客にとって“今何が必要か”を議論する際の共通基盤となり、社内の顧客理解を加速させる存在なのです。
そもそも「顧客の健康」とは何を意味するのか?

「ヘルススコアは顧客の健康状態を表す」とはよく言われますが、ここで使用される“健康”とは一体何を指すのでしょうか。体温や血圧のように絶対的な基準があるわけではなく、業種や商材、顧客層によって、その定義は大きく異なります。
たとえば、あるBtoB SaaSプロダクトにとっては「導入初月にすべての機能を利用していること」が健康な状態かもしれません。しかし別の企業では、「定期的な活用があり、担当者との関係性が良好であること」が健康の定義かもしれません。つまり、「その顧客にとって、サービスの価値が適切に届き、継続する理由がある状態」が“健康”といえるのです。
このように、「健康=プロダクトの利用状況」だけではありません。契約更新の意志やサービス満足度、トラブルの有無、人的関係の強さなど、定量・定性を問わず多面的な要素を加味することで、はじめて“本当の健康”が見えてきます。ヘルススコアは、それらを1つのスコアに集約し、意思決定を促す道具として設計されるべきなのです。
どんなスコアが「良いスコア」なのか?目的に応じた設計の考え方
ヘルススコアに正解はありません。業界や製品、顧客の性質によって、「良い状態」とみなす基準は異なります。だからこそ、導入前には「何のためにこのスコアを使うのか?」という目的意識が極めて重要になります。
たとえば、「解約リスクの予兆を察知してアラートを出す」ことを目的とする場合、短期的な変化を捉えるスコア設計が求められます。一方で、「ロイヤルカスタマーの条件を明らかにし、再現性ある成功パターンを見つけたい」という場合には、長期的な利用履歴や満足度傾向に基づいたスコア構成が必要です。また、プロダクトの特性によっても異なります。あるSaaSでは、週に数回の利用が「正常」とされるのに対し、別のサービスでは月1回のログインでも十分ということもあります。よって、業界ベンチマークを鵜呑みにせず、自社のプロダクトにとって「理想的な活用パターンとは何か?」を定義し、それに基づくスコアリングロジックを構築することが重要です。
さらに、スコアを構成する各指標の「重みづけ」も大きな設計ポイントです。機能の利用頻度に重きを置くのか、それともサポートへの依存度に注目するのか。全体のスコアがバランスを欠くと、誤ったアラートや判断を導いてしまうリスクもあるため、はじめは手探りでの設定になりますがPDCAを回しながら継続的に見直すことで精度を高めることが可能です。
ヘルススコアの実践活用例 ― 営業、CS、プロダクトの現場での使い方

ヘルススコアは単なるモニタリング指標ではなく、営業やカスタマーサクセス、プロダクト部門など各部門の意思決定を支える実用的な指標でもあります。ここではヘルススコアの具体的な活用シーンを3つの部門に分けて紹介します。
営業部門でのヘルススコア
営業部門においては、アップセル・クロスセルのタイミングを見極めるためのシグナルとしてヘルススコアが使われます。スコアが高い数値を継続しているもしくは上昇傾向にある顧客は「サービスへの理解と活用が進んでいる」と判断され、追加提案の成功確率が高いと考えられます。逆にスコアが急落している場合は、なにかしら不満を抱えていたり、活用促進が進んでいないなどの原因が考えられるためフォローアップを優先すべき対象と考えられます。
カスタマーサクセス部門でのヘルススコア
カスタマーサクセス部門では、オンボーディングの進捗や、アダプションフェーズの定着度合い測定に使われます。たとえば、導入後30日以内に一定のスコアを超えていなければ、定着が進んでいないと考えられるため追加のトレーニングや支援が必要と判断する運用が可能です。ヘルススコアから読み取り顧客がの問題が顕在化する前に先回りして対処する「プロアクティブな対応」を実現することで顧客満足度の向上も期待できます。
プロダクト部門でのヘルススコア
プロダクト部門では、機能の利用状況を可視化し、どの機能が「健康維持に寄与しているか」を定量的に把握する手段としてスコアを参照します。たとえば、Aという新機能の利用がスコアの向上と相関する場合、その機能をより多くのユーザーに届けるためのUI改善や導線設計の改善が行われることもあります。
ヘルススコアに活用すべき主要指標とは? ― 効果的なスコア設計の第一歩

ヘルススコアを構築するうえで、どの指標を組み込むべきかは非常に重要な論点です。選ぶ指標次第で、スコアの意味が大きく変わり、現場のアクションにも直結します。ここでは、ヘルススコアに活用されやすい代表的な指標と、その背景にある考え方を紹介していきます。
プロダクトの利用状況
まず、最も基本的でかつ重要な指標が「プロダクトの利用状況」です。ログイン頻度や操作回数、利用している機能の種類、滞在時間などが代表的な項目です。たとえば、月に10回以上ログインしているユーザーと、1回しかログインしていないユーザーでは、サービスとの関係性がまったく異なります。また、単なるログイン数だけでなく、「複数機能の併用」「最新機能の利用」「管理者設定の活用」など、利用の“深さ”に着目することも、顧客の成熟度を測るうえで有効です。
サポート・問い合わせ状況
次に「サポート・問い合わせ状況」です。頻繁に問い合わせをしている顧客が一概に“悪い状態”とは限りませんが、同じ質問が繰り返されている場合や、トラブル対応ばかりが続いているような場合には注意が必要です。一方で、まったく問い合わせがない顧客も、「実は使われていない」「担当者が困っていても声をあげていない」可能性があるため、油断はできません。サポートとの接点の“質と量”を見極めることがポイントです。
契約情報
さらに、「契約情報や課金履歴」も重要なデータです。例えば、過去に契約更新を何度も行っている顧客は、利用度が高く継続意志も高いとみなされます。また、利用ユーザー数の増減、プラン変更履歴、課金額の推移なども、利用拡大や縮小の兆候を示すサインとして有効です。特にBtoBでは、利用アカウントの増加がそのまま企業の活用度を示すことも多く、定点観測すべき指標のひとつといえるでしょう
定性的な情報
定性的な情報も無視できません。たとえば「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」や「CSAT(カスタマー・サティスファクション・スコア)」といったアンケート結果は、顧客の主観的な満足度を示すシグナルになります。数値としては小さくても、離反の予兆を見抜く上ではとても有効です。特に、ヘルススコアの定量データとNPSのスコアに乖離がある場合――たとえば利用はされているのにNPSが低いといったケースは、サービスに対して何かしら不満を持っていると考えられ、早期に手を打つべきサインといえるでしょう。
その他の情報
その他、「契約担当者との定例ミーティング出席率」や「マーケティングコンテンツへの反応」「コミュニティへの参加有無」「セミナー出席回数」なども、カスタマーエンゲージメントの指標として活用されることがあります。こうした周辺活動からも、顧客が製品やサービスにどれだけ関心を持っているかを推測できます。
このように、ヘルススコアは一つの数字でありながら、その裏には複数のデータソースと視点が存在しています。重要なのは「スコアを上げるための指標を選ぶ」のではなく、「顧客が成功している状態とは何か?」という定義を起点に、指標を設計していくことです。指標が実態を反映していなければ、スコアは単なる幻想に過ぎません。だからこそ、ヘルススコアを本当に意味あるものにするには、データの整備と現場のリアリティの両立が求められるのです。
ヘルススコア導入の落とし穴と成功のためのポイント

一方で、ヘルススコアは「万能な魔法の指標」ではありません。導入時にありがちな落とし穴としてまず挙げられるのが、「スコアに振り回されてしまう」ことです。過度に数値の上下に一喜一憂したり、背景を分析せずにアクションを起こすと、本質的な問題解決につながらないばかりか、顧客との関係を悪化させる恐れもあります。
また、スコアの根拠がブラックボックス化してしまうと、現場の納得感が得られず、スコアが単なる「飾り」になってしまうこともあります。導入初期は、スコアを構成する指標やその理由を関係者に丁寧に説明し、共通理解を得ることが大切です。
もうひとつの課題は「データの整備」です。スコアの精度は、元となるデータの正確性と網羅性に大きく依存します。CRMやMAツールとの連携が不十分な場合、スコアの信頼性が担保されず、むしろ判断を誤るリスクを増大させてしまう可能性があります。よって、導入にあたってはデータ基盤の整備と、継続的なメンテナンス体制の構築が不可欠です。
まとめ
今後のビジネスにおいて、顧客理解はますます高度化・複雑化していきます。顧客一人ひとりの状況をリアルタイムで把握し、最適なアクションを選択する能力こそが、競争優位を生む重要な要素となるでしょう。その中で、ヘルススコアは単なる数値指標ではなく、「顧客との関係性を深めるための道具」として進化を遂げていくはずです。
AIや機械学習の活用により、より精度の高いスコアリングや予測が可能になりつつあります。加えて、スコアが自動的に変動し、それに応じてカスタマージャーニーや提案内容が動的に最適化される未来も、決して遠くはありません。
ただし、どれほど技術が進歩しても、最終的には「誰のために」「何のために」ヘルススコアを使うのかという本質的な問いが重要です。顧客と向き合い、信頼関係を築くための一つの手段として、今こそヘルススコアの導入・活用に踏み出す価値があるといえるでしょう。

執筆者情報:
佐々木 一稀(ささき かずき)
ユニリタ自社開発のフローチャートツール「Ranabase」にて開発に携わり、カスタマーサポートを担当し2022年に「Growwwing」チームへジョイン。
カスタマーサクセスメンバーとしてオンボーディング支援業務を経験し、現在ではその知見を活かし顧客の求めてる情報を発信するためにマーケティング分野を担当。
幅広い経験からの視点を生かし、カスタマーサクセスを行う方へのヒントとなるような記事を掲載できるよう全力で頑張ります。