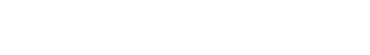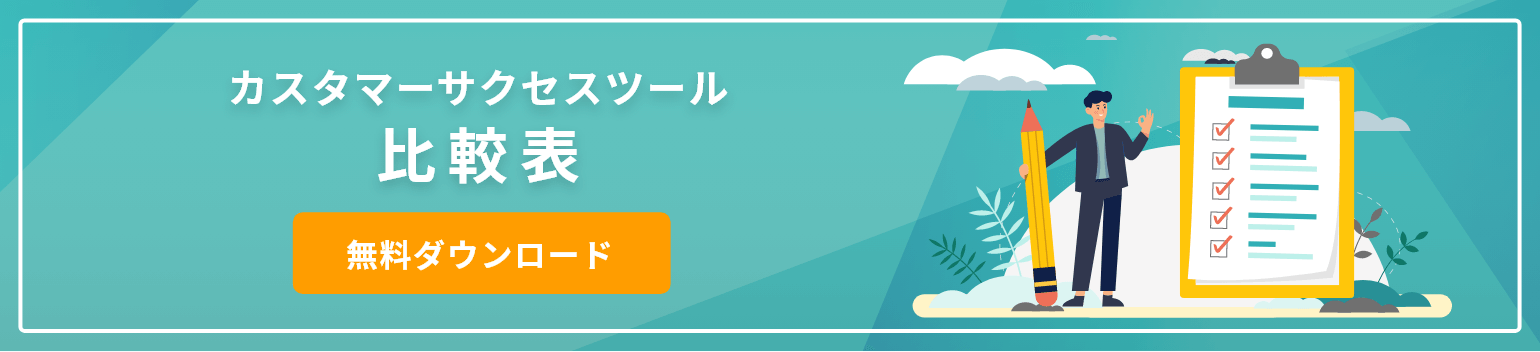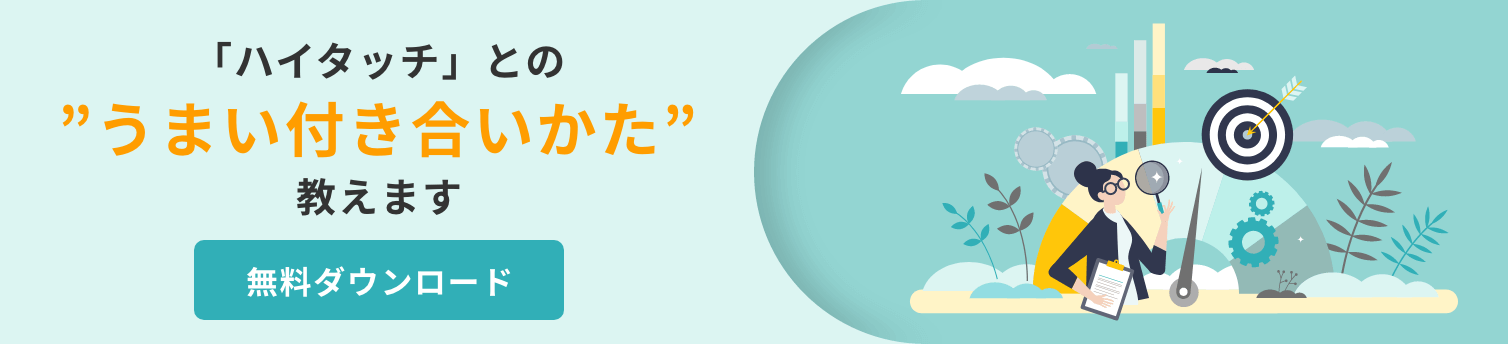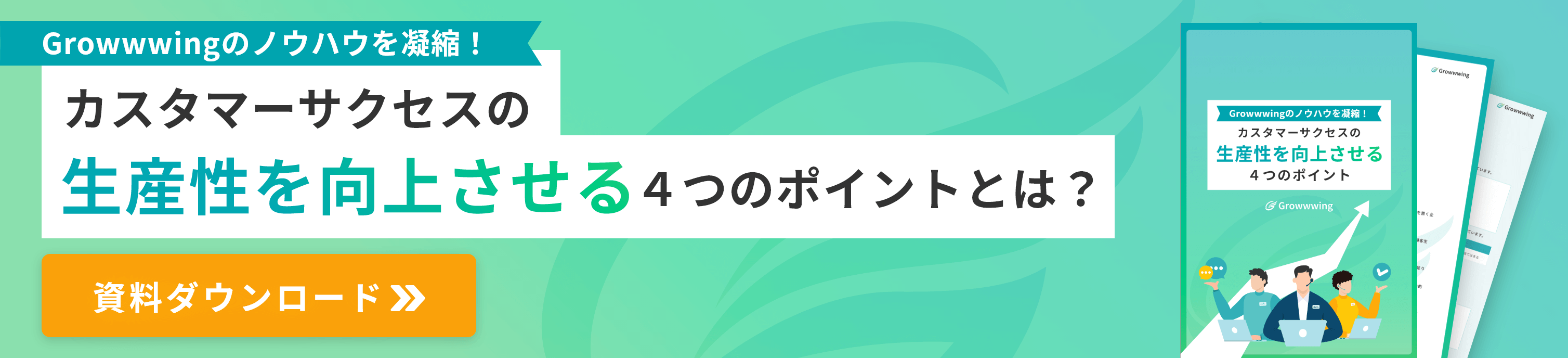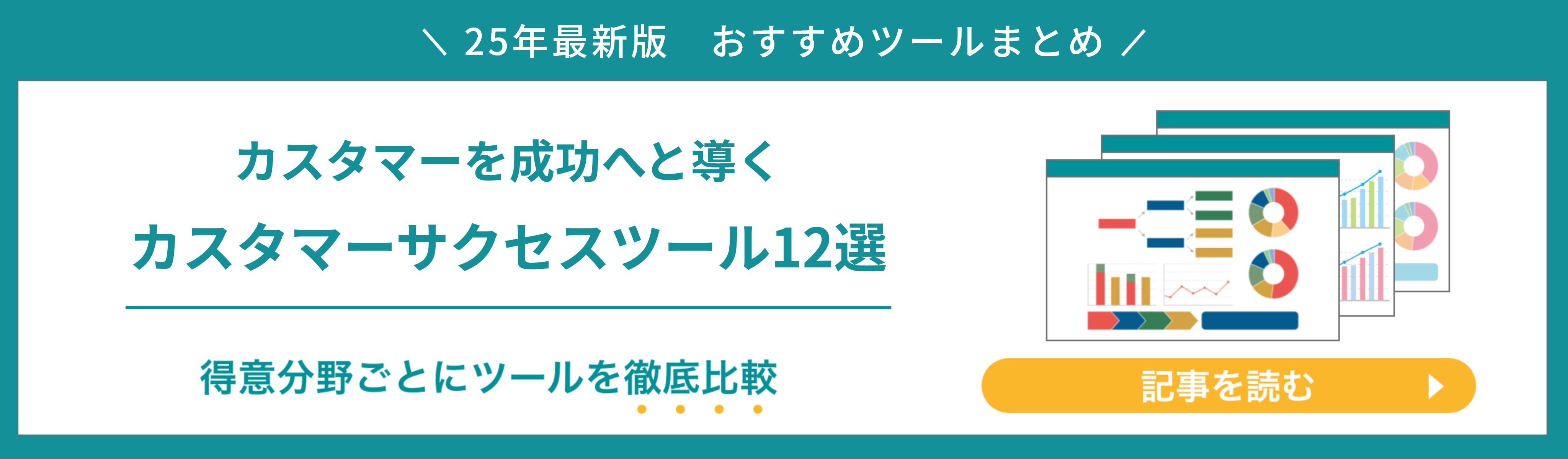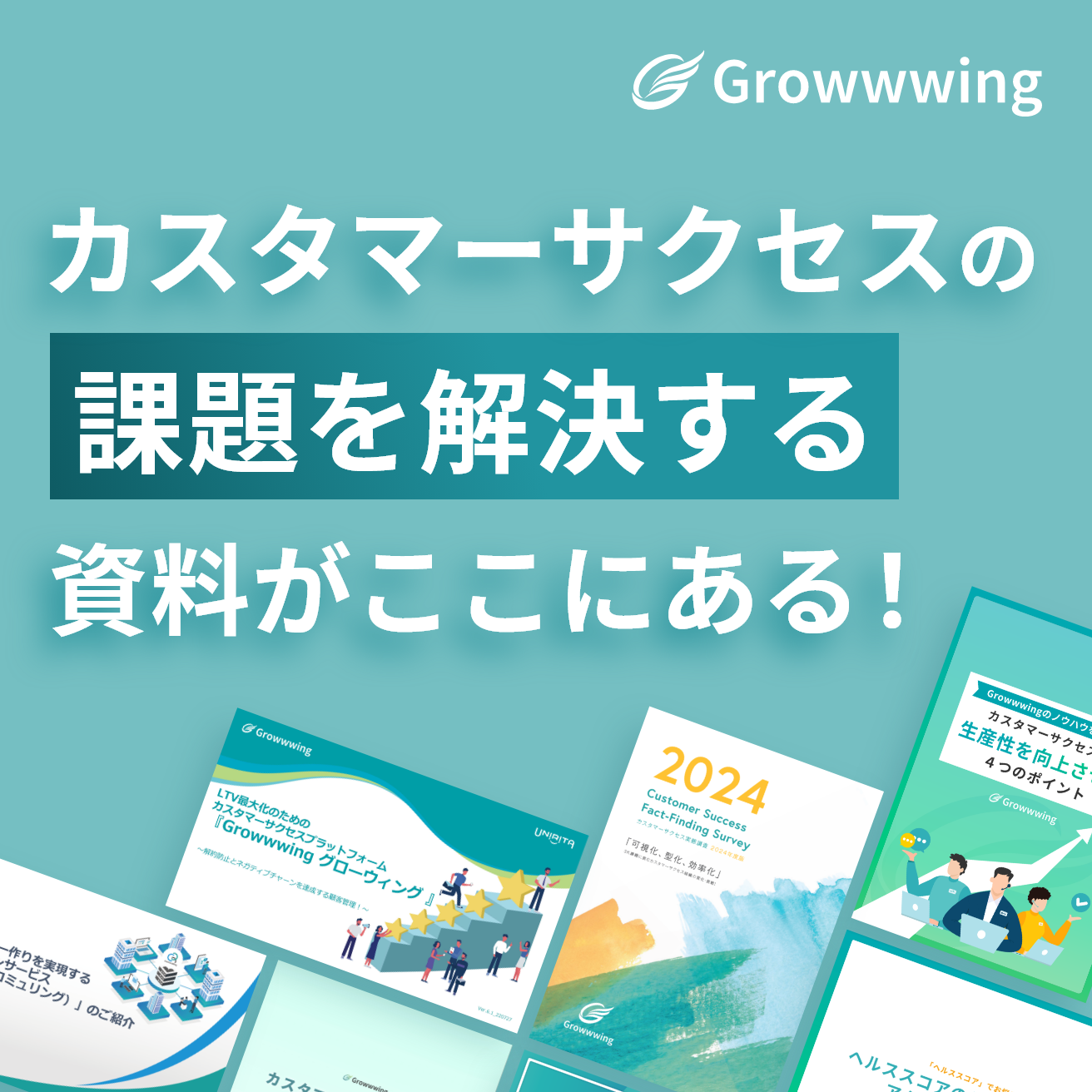【応用編】LTV、KGI、KPIの理解と適切運用でサブスクリプションビジネスの成長を促進!
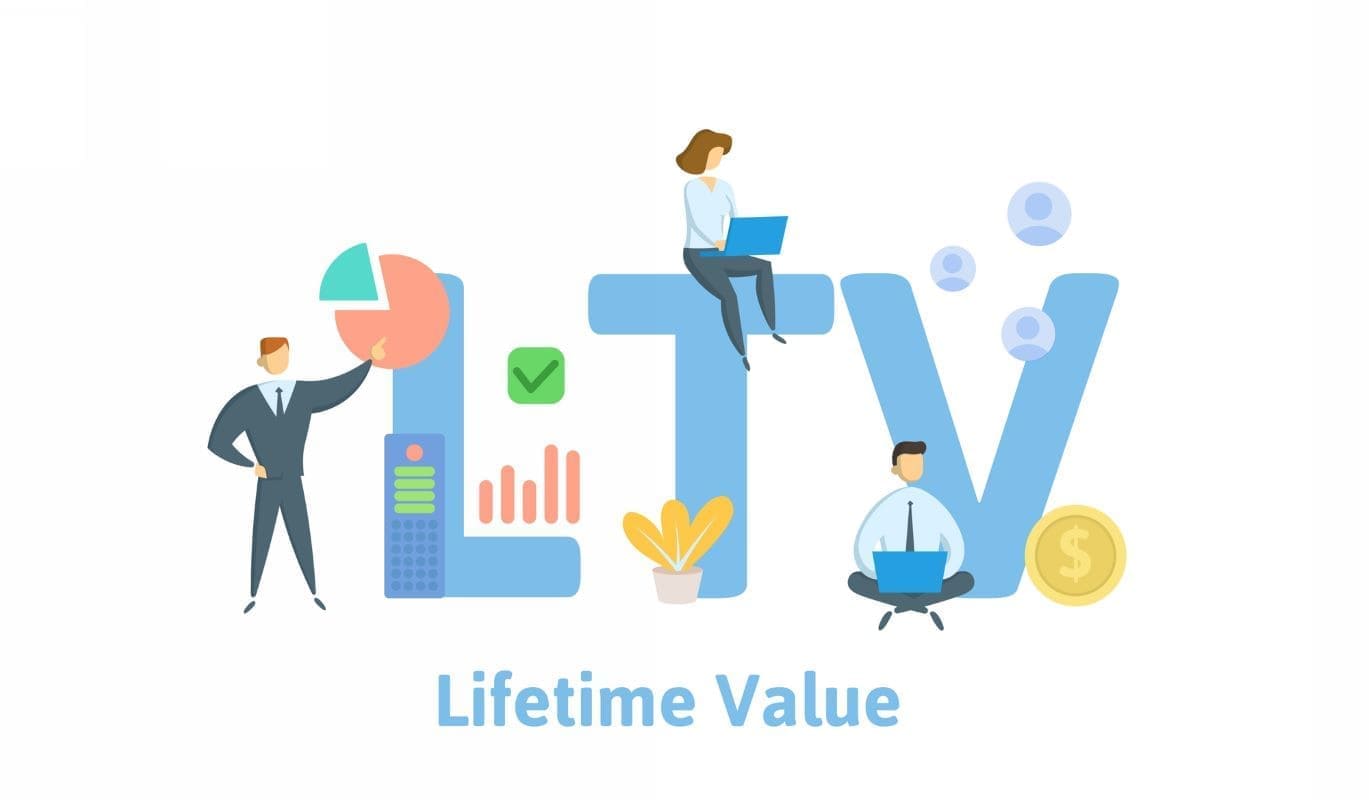
カスタマーサクセスにおいて重視されるキーワードとしてよく出てくる「LTV 」「KGI」「KPI」ですが、用語の意味は理解していても、実運用における実践的な適用方法や、それぞれの相関関係を正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。SaaS / サブスクリプションビジネスを効率よく成長させるには、これらの指標を「実際に使える」スキルが必要です。
本記事では3つのキーワードの意味をおさらいしながら、相関関係や事例を用いた実運用手法まで詳しく解説します。
LTV、KGI、KPIの"意味"についておさらい

最初にLTVとKGI、KPIについて、一般的な意味や概念をおさらいしておきましょう。
LTVとは
「LTV(Life Time Value)」は「顧客生涯価値」と訳され、ある顧客が特定の企業やブランドと取引を始めてから終了するまでの期間に、どれだけの利益をもたらしてくれるかを算出した数値です。ストレートに表現すると、ある顧客から徴収している月(年間契約の場合は「年」)額に、契約継続月数を掛け合わせたもの、ということになります。事業全体を見る場合は、全契約顧客のLTVの平均値を算出して指標とするのが一般的といえます。
LTVを把握することで、優良顧客の分析や自社プロダクト・サービスの利益体質、顧客の獲得コストと維持コストなどの目標設定など、事業運営上のさまざまな活動の指標として利用できます。また顧客との継続的な関係維持により収益を生み出すSaaS / サブスクリプションビジネスでは、顧客の累計売上を定量化したLTVは重要な指標となります。
LTVが重視されるようになった背景
LTVが重視されるようになった理由の1つとして、サブスクリプションの浸透といったビジネスモデルの変化が挙げられます。モノからコトへと消費が変化するなかで、多くの企業がSaaSに代表されるサブスクリプションビジネスへの転換を図っています。顧客との長期継続で収益が安定するSaaS型ビジネスでは、LTVの最大化がゴールとなるため注目されるようになったのです。
また飽和している国内市場はコモデティ化が進み、プロダクトやサービスの差別化が難しくなっています。新たな価値を提供して新規顧客を獲得することは、既存顧客維持よりも一層コストがかかることになります。企業は収益安定化のためにも既存顧客との関係性を強化するようになり、LTVが重視されるようになりました。
LTVの算出式
LTVとひとことでいえど、実際に運用する際には、
・いち顧客あたりの平均LTV
・事業全体のLTV
・解約や新規追加獲得契約などを加味する精緻なLTV
など、様々な切り口で算出する必要があります。
▶各種LTVの詳しい計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
LTVを最大化するには
サブスクリプションビジネスでは、LTVの最大化が最終目的となります。LTVを最大化するには、「契約期間の長期化」と「契約単価の高額化」が大きな要因となります。これらを実現する具体的な方法を解説しましょう。
①チャーンレート(解約率)を下げる
「契約期間の長期化」を妨げる最大の要因は、契約継続を終了するチャーンです。LTVを向上して最大化するには、チャーンレートを下げる対策が必要となります。
▶チャーンレートの下げ方はこちらを参照ください。
②アップセル・クロスセルによる顧客単価の向上
「契約単価の高額化」を図るには、アップセルやクロスセルが有効です。顧客の状況に合わせて上位プランへのアップグレード提案や、セット販売など他の製品やサービスの追加購入を促すなどを行います。
KGIとは
「KGI(Key Goal Indicator)」は「重要目標達成指標」と訳され、事業やプロジェクトなどのビジネスゴールの達成度合を測る指標のことです。売上や利益、利益率や販売数などを設定するのが一般的です。
KGIを設定することで、事業目的や意図を関わるスタッフや従業員間で共有できます。進捗を確認しながら目標に向かって進むための、モチベーションを維持できるメリットもあります。
KPIとは
「KPI(Key Performance Indicator)」は「重要業績評価指標」と呼ばれ、KGIを達成するためのプロセスが適切に実施されているかを定量的に評価する指標のことです。KGIが最終目標であるのに対し、KPIは中間指標となります。
プロセスを確認する定量的な目標でわかりやすい数値を設定することで、達成度や進捗を把握しやすくなります。
LTV、KGI、KPIの相関関係はどのようなもの?
続いて、LTVとKGI・KPIの関係性を整理しておきます。特にSaaS / サブスクリプションビジネスに適したKGI・KPIは、カスタマーサクセスの実践で活用できるので理解しておきましょう。
KGIのためのKPI、LTVはときによりKGIにもKPIにも
前述の通り、KGIが最終目標で、KPIはKGIを達成するための指標という相関関係があります。例えば今月末までに新規契約10件というKGIを立てた場合、1週目で3件、2週目までに5件と、KGI達成までの期間を細分化し、当該期間それぞれで達成すべき数字も細分化するといった「時間軸」でのKPIがまず挙げられます。また、新規契約10件のKGIを達成する際、過去累計の成約率が10%だったとすると、契約前のプロセスとなる有効商談の数は、最低100件必要ということになり、これは「プロセス軸」のKPIという捉え方になります。
LTVは、SaaS / サブスクリプションビジネスの事業規模そのものを指す言葉であるため、「KGI」として設定されるのが一般的といえます。ただし、たとえば事業の目的が一定水準のLTVを達成した上での「売却」にあるとすれば、その場合KGIは「当該事業の売却額」ともいえますし、いち企業の中で「10のSaaS / サブスクリプション事業を立ち上げる」といったことが目標となっていれば、その中のいち事業におけるLTVも、中間指標たるKPI、といえなくもありません。このように、「LTV」や「MRR/ARR」といった言葉は、それぞれ「一定の期間や定義」における「収益額を表現する言葉」として絶対的な意味を持ちますが、それらがKPIなのかKGIなのかは、当該の事業の状況や環境にもとづいて相対的に変化していく、ということを理解しておく必要があります。
サブスクリプションビジネスでよく用いられるKGI
前述のLTV、MRRといった、SaaS / サブスクリプションビジネスにおいて、KGIとしてもちいられることが多い言葉の定義をここで再確認しておきます。
ARR(Annual Recurring Revenue)
ARRとは「年間経常収益」や「年間定期収益」とも呼ばれ、毎年決まって得られる収益のことです。売上や収益がKGIであれば、ARRも確認しておきたい指標となります。
MRR(Monthly Recurring Revenue)
ARRが年次の収益額であるのに対し、MRRは同じ概念のもと、集計期間を月次にしたものになります。
ACV(Annual Contract Value)
ACVは「年間契約額」のことで、顧客契約ごとの平均年間収益です。KGIとしての売上・利益をさらに細分化して、ACVをKGIとすることもあるでしょう。
LTV
サブスクリプションビジネスの最終目標はLTVなので、LTVをKGIと設定することもできます。継続率やARPAなど重要な指標の影響度も把握できるため、SaaSビジネスにおいては売上・利益と共に重要な指標といえます。
サブスクリプションビジネスのKPI測定に適した指標
KGIを達成するために、業務プロセスが適切に行われているかを定量的に管理・評価するのがKPIです。サブスクリプションビジネスに適したKPIは、収益性の根拠となる以下のような指標が妥当です。
チャーンレート(解約率)
サブスクリプションビジネスは継続利用が前提なので、チャーンレートが重要な指標となります。継続と解約を定量化し、月ごとに比較すると右上がり・右下がりが明確になります。
チャーンレートには、一定期間内の解約ユーザー率がわかる「カスタマーチャーンレート」と、収益ベースで算出する「レベニューチャーンレート」があります。計算式は以下のとおりです。
カスタマーチャーンレート = 月間の解約利用者数 ÷ 月初の利用者数(解約前の利用者数)
レベニューチャーンレート = その月に解約によって減少したMRR ÷ 前月末のMRR
※MRR(Monthly Recurring Revenue):月次経常収益
チャーンレートの推移を分析することでユーザー数や動向予測が可能となり、中長期の売上見込みや資金計画などの指標となるため、KPIとして必ず把握しておきたい数値です。
オンボーディング完了率
オンボーディングとは、カスタマーサクセスにおける最初のフェーズのことで、顧客がサービスを導入してから運用定着するまでの段階です。オンボーディングが完了した顧客は、プロダクトやサービスの価値を理解しているためその後も安定継続の可能性が高いことから、オンボーディング率もKPIとしての重要な指標となります。
売上継続率
売上継続率は「NRR(Net Revenue Retention)」ともいわれ、既存顧客の売上がどれだけ維持されているか、どれだけ拡大しているかを判断する指標です。サブスクリプションビジネスでは重要なKPI指標となり、売上継続率が下がっていたら、プロダクト・サービスの訴求力や有効性が低下している可能性があるので対策が必要となります。
計算式は以下となります。
NRR(%) = ( 月初のMRR + アップセルによる収益Expansion MRR –ダウングレードによって減った収益Downgrade MRR– 解約により減った収益Churn MRR ) ÷ 月初のMRR × 100
アクティブユーザー率
アクティブユーザー率とは、特定のサービスを契約中の顧客の中で実際に利用している顧客の割合です。アクティブユーザー率が高いと継続利用を見込め、サービスの価値を評価していると判断できることから、売上継続率の維持など利益向上を期待できます。一方利用していないユーザーは解約につながりやすいため、対策が必要です。
セッション期間
セッション期間は顧客がサービスを利用し続けた契約期間のことで、LTVや売上向上には長期継続が必要なことから重要なKPI指標となります。
顧客平均単価(Average Revenue Per Account)
顧客単価(ARPA)もKPIとなりうる指標です。1アカウント(契約者)あたりの平均単価のことで、1ユーザーを対象にする場合はARPU(Average Revenue per User)を使用します。ARPAは1契約に対して複数のアカウントが発行できるサブスクリプションサービスなどのKPIに適しています。
ARPAの計算方法は以下となります。
ARPA = 売上 ÷ 契約者数
NPS(顧客推奨度)
顧客ロイヤルティを数値化するNPSは、サブスクリプションビジネスの直接的なKPIにはなりづらいものの、参考値としては有効です。将来的な収益性や顧客のLTV向上などの可能性を探ることができるため、経営判断のいち指標として活かすのがよいでしょう。
LTV最大化のためのカスタマーサクセスプラットフォーム『Growwwing グローウィング』のサービス資料を無料でダウンロードいただけます。『Growwwing 』サービス資料を無料でダウンロード
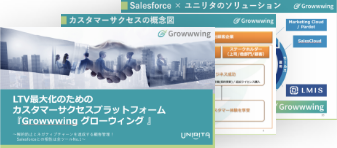
『Growwwing グローウィング 』は、解約防止とネガティブチャーンを達成する顧客管理が実現。Salesforceとの相性は全ツールNo.1です。
サブスクリプションビジネスのKGI・KPI設定のポイント
サブスクリプションのKGIやKPIを設定する際に注意したいポイントを解説します。
KGIを達成できるKPIにする
KPIは最終的なゴールであるKGIを達成するための中間目標です。KGIを達成するためのプロセスを整理して各段階で達成すべき指標なので、KGIに直接結び付かないKPIを設定しないよう注意しましょう。
定量化できる指標とする
KGIもKPIも、必ず数値で設定できる指標とします。定量的に把握できる指標にすることで、施策やモニタリングの効果検証が行いやすくなります。また目標がわかりやすくなり、メンバー間の認識のズレも防げられます。
部門間で共有・連携する
カスタマーサクセスの成功は、カスタマーサクセス部門のみの活動で達成できるものではありません。決定したKGI・KPIは、営業やマーケティング、カスタマーサポート部門などと共有し、達成へ向けて協力し合える体制を作ることが重要です。
PDCAを定期的に行う
適宜PDCAを回して、達成確認や改善を図ることもポイントです。客観的・定量的に測定できるKPIは分析・検証もスムーズです。また経営方針の変更や社会情勢の変化などによりKPIも変えなければいけない場合もあるため、見直しやすい項目をKPIに設定するとよいでしょう。
LTV/KGIが伸びない原因別【KPIの設定方法とあるべきCS活動】
ここからは、LTVやKGIの伸びが思わしくない場合のKPI設定方法やカスタマーサクセス活動について、原因別に紹介します。KGIやLTVは、解約率や継続率、ARPAなどの顧客単価など、KPIとなる要素が大きく影響しています。LTV・KGIが伸び悩んでいる場合は、停滞に最も影響している要素を突き止め対処することが重要です。
新規契約数が少ない
新規契約を増やすには、カスタマーサクセスのタッチモデル(ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチ)を活用して、テックタッチの対策を行います。LTVは低くとも対象となる顧客数が最も多いテックタッチを行い、自社に利益をもたらしてくれる顧客を獲得・創出するようにしましょう。
チャーンレート(解約率)が高い
顧客の期待と提供価値に差がある場合
顧客の期待と提供価値に差がある場合は、最低利用期間を過ぎればすぐに解約されてしまいます。利用開始直後に起こりやすいこのパターンは、オンボーディングを強化することで早期解約を防ぎます。いち早くプロダクトやサービスに慣れてもらうようサポートを行い、利用を通じた成功体験や価値の実感を数多く提供します。顧客に適した体験価値を提供できるように、事前リサーチや分析をしっかりと行っておくことが重要です。
利用頻度が下がる・利用機能が限られる場合
プロダクトやサービスの利用頻度が下がる、利用機能が限定され始めたら、解約の兆候が見えています。
担当者を通じて利用状況や不満・要望などの顧客状況を把握し、解約の兆候を捉えて早期に改善策を講じる必要があります。
不満が発覚した場合
顧客からの問合せなどで不満が発覚した場合は、解約の危機が迫っています。不満や要望を明らかにして、迅速に対応しなくてはなりません。また、日頃から問い合わせに対する迅速かつ的確な回答を行える体制作りや対応の成功事例のマニュアル化など、解約率の改善につながる環境整備や準備も行っておくようにしましょう。
顧客単価が低い
顧客単価が上がらずLTVや売上の伸び悩んでいる場合は、プロダクト・サービスの単価を上げるほか、アップセル・クロスセルで対応します。顧客が納得する範囲で単価の値上げを行う、サービスプランのバリエーションを増やして上位プランを提案する、セット購入の多い製品を提案するなど、顧客の状況やニーズに合わせた対策を行うとよいでしょう。
購買頻度が低い
購買頻度が低い場合は、顧客との接触回数を増やして適切なタイミングでアプローチするのが効果的です。具体的な手法としては、顧客に対して定期購入やリピートを促すステップメールや、リマインドメールなどがあります。プロダクトやサービスに対してある程度理解が深まった段階で、対面によるアプローチに移行するとよいでしょう。
顧客獲得・運営コストが高い
顧客の獲得や運営に高いコストがかかっていると、利益を圧迫してしまいます。現状行っている施策の効果をしっかりと分析し、費用対効果の高い施策に注力していくことでコスト削減を目指しましょう。また、タッチモデルによるターゲットと対策の整理も、人的リソースやコストの最適配分を可能にします。
LTVとKGI・KPIの相関関係を理解して最適解を導きだす
LTVとKGI・KPIは相互に強い関連性があり、それぞれが向上・最大化することによってカスタマーサクセスの成功につながります。KGIの要素はKPIであり、さらにKPIはLTVの要素に分解できるため、KGIで設定している売上や利益が伸びない場合やLTVが向上しない場合は、どの要素に問題があるかを分析することで、要因を明確にできます。
カスタマーサクセスを成功させるなら3つの相関関係や連携の度合いを理解して、対策を組むようにしましょう。
執筆者情報:
渡邉 剛(わたなべ ごう)
ユニリタ自社開発のETLツール「Waha! Transformer」の導入教育/サポート、データ活用システム(ETL/DWH/BI)構築のプロジェクトマネージャーを歴任し、2018年にカスタマーサクセスチームの立上げ責任者を担当。
その経験からカスタマーサクセス専用ツールの必要性を実感し「Growwwing」の事業立上げをおこなう。
2020年7月の事業化からプロダクトマーケティングとカスタマーサクセスの責任者を担当。
カスタマーサクセスコミュニティ「CS KOMMONS」においてハイタッチ部 副部長も歴任。